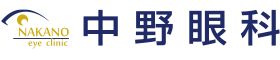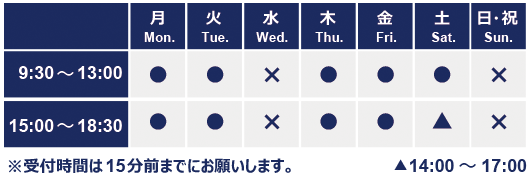よくあるご質問(Q&A)
- Q暗い場所で目が慣れにくいのは病気ですか?
- A
通常、人の目は暗所に入ると10〜30分で“暗順応”します。もしそれが極端に遅かったり、夜になると見えにくくなるようであれば、「夜盲症」という視覚障害の可能性があります。
- Q夜盲症は遺伝ですか? それとも後天的なもの?
- A
遺伝性疾患(例:網膜色素変性症)が原因のこともありますが、ビタミンA欠乏や薬剤性など後天的な夜盲症も存在します。病因により治療可能性が異なります。
- Qどんな検査をすればわかりますか?
- A
視力・視野検査に加え、暗所視力の検査や網膜電図(ERG)、眼底検査、栄養評価などが行われます。自覚症状があれば眼科受診をおすすめします。
はじめに
「暗いところに入ると何も見えない」「夜道を歩くのが怖い」「周囲の人は見えているのに自分だけ見えない」――このような経験はありませんか?
日常生活では見逃されがちですが、こうした暗所での視覚障害は“夜盲(やもう)”と呼ばれ、特定の疾患や栄養状態の異常によって引き起こされることがあります。
本稿では、検索ニーズの高い「暗所 見えない」「夜盲症とは」といったキーワードに対し、夜盲症の定義と原因疾患(ビタミンA欠乏症・網膜色素変性症など)を中心に解説します。
1. 夜盲症とは何か
夜盲症(やもうしょう、Nyctalopia)は、暗い場所や夜間に視力が著しく低下する状態を指します[1]。
通常、明るい場所から暗所へ移動すると、瞳孔が拡がり、網膜の桿体細胞が光に順応することで、徐々に見えるようになります(暗順応)。
夜盲症ではこの適応がうまく働かず、極端な見えにくさや、暗所での失明に近い視覚障害をきたすことがあります。
暗所での見えにくさには個人差がありますが、明らかに「自分だけ見えない」「暗いところでつまずく」といったケースでは、視機能検査が望まれます。
2. ビタミンA欠乏症による後天的夜盲
ビタミンA(レチノール)は、網膜の視細胞で光を感じるために不可欠な物質であり、特に暗所視に関与する桿体細胞の機能に深く関係しています[2]。
発展途上国では栄養失調によるビタミンA欠乏が依然として失明原因となっていますが、日本国内でも以下のような要因で発症する例があります[3]:
- ・極端な偏食、ダイエット、摂食障害
- ・胆道閉塞や慢性膵炎など、脂溶性ビタミンの吸収障害
- ・長期の肝疾患、アルコール性肝障害
ビタミンA欠乏による夜盲症は、原因を補えば視機能が改善する可能性が高いため、早期発見が極めて重要です。
3. 網膜色素変性症などの遺伝性疾患
夜盲を呈する代表的な遺伝性疾患が網膜色素変性症(Retinitis Pigmentosa:RP)です。これは桿体細胞が徐々に変性・消失していく進行性の疾患で、日本では1万人に1人程度の頻度とされています[4]。
初期は夜盲として発症し、進行すると視野が狭くなる(求心性視野狭窄)、やがて昼間の視力も低下することがあります。
現在、有効な治療法は限られていますが、視機能補助具・遺伝カウンセリング・生活支援などを通じて生活の質を維持する支援が行われています[5]。
また、アッシャー症候群(RPに難聴を伴う)など他の遺伝疾患でも夜盲が初発症状となることがあります。
4. その他の原因:薬剤・眼底疾患・加齢性変化
一部の薬剤(例:高用量のクロロキン、フェノチアジン系抗精神病薬など)は網膜毒性を持ち、夜間視力低下をきたすことがあります[6]。
また、加齢や眼底出血・糖尿病網膜症などでも、暗所視力が低下する場合があります。
夜盲=すぐに網膜色素変性というわけではなく、鑑別診断には全身の病歴・内科的評価が重要です。
おわりに
「暗いところが見えない」「夜道が怖い」といった症状は、しばしば軽視されがちですが、夜盲は明確な視覚障害であり、背景に治療可能な疾患が隠れていることもあります。
ビタミンA欠乏のように栄養補充で改善可能なものから、遺伝性の進行性疾患まで、原因の幅は広いため、自己判断ではなく眼科での評価が重要です。
見えづらさを“年のせい”にせず、一度専門医にご相談ください。
参考文献
[1] 日本眼科学会. 眼科診療クオリティブック. 医学書院, 2020.
[2] Sommer A. Vitamin A Deficiency and Clinical Disease: An Historical Overview. J Nutr. 2008;138(10):1835-1839.
[3] Nishikawa T, et al. Vitamin A deficiency-induced night blindness in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res. 2008;38(7):709-713.
[4] Hartong DT, et al. Retinitis pigmentosa. Lancet. 2006;368(9549):1795-1809.
[5] Bittner AK, et al. Vision rehabilitation for retinitis pigmentosa. Cochrane Database Syst Rev. 2020;8(8):CD010527.
[6] Bernstein HN. Ocular safety of hydroxychloroquine. Ann Ophthalmol. 1991;23(8):292-296.