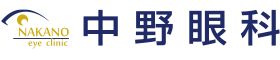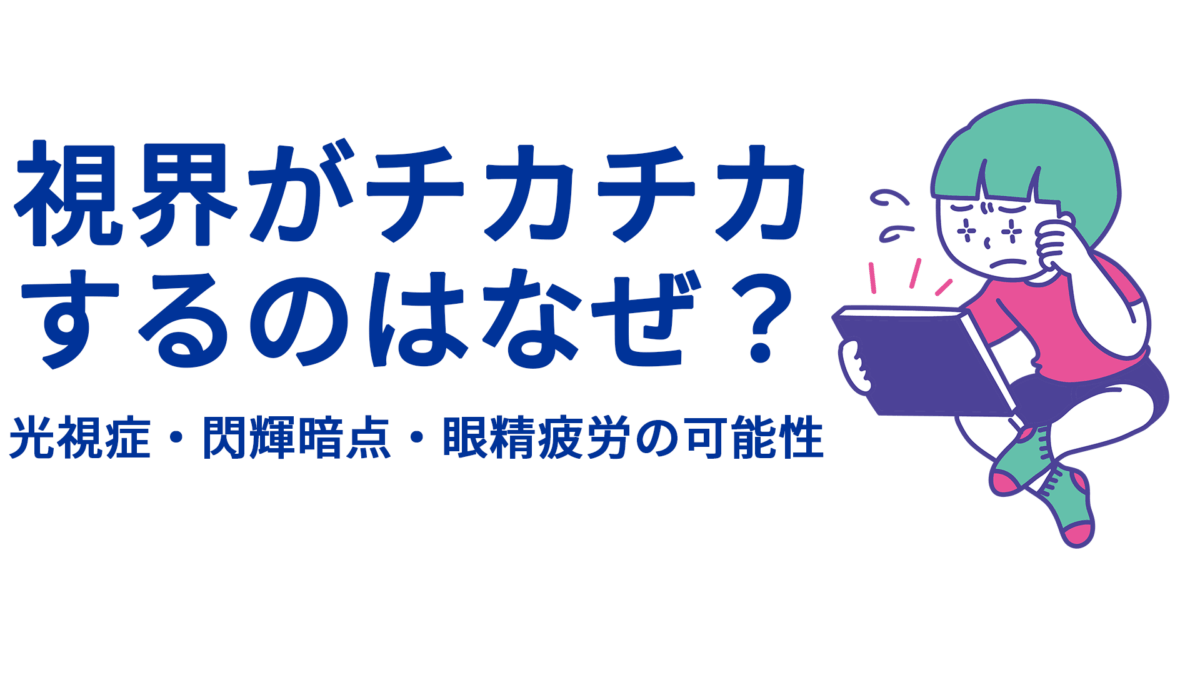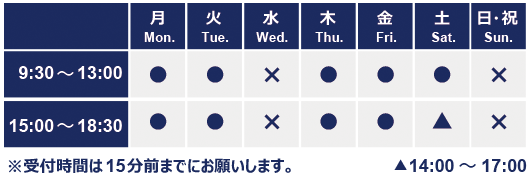よくあるご質問(Q&A)
- Q視界がチカチカするのは、どんな病気のサインですか?
- A
代表的には「光視症(網膜の刺激)」「閃輝暗点(片頭痛の前兆)」「眼精疲労」によるものが挙げられますが、網膜裂孔や脳の異常が隠れていることもあり、注意が必要です。
- Q両目ともにチカチカするのは問題ですか?
- A
両眼に共通して見える場合は、目ではなく脳(後頭葉)由来の症状の可能性があります。閃輝暗点はその一例です。
- Q片目だけがチカチカします。これは眼科の病気ですか?
- A
片目だけで起きるチカチカは、網膜や硝子体の異常による光視症の可能性が高く、早期の眼底検査が推奨されます。
- Q一瞬だけなら様子を見てもいいですか?
- A
たった一度であっても、「急に黒いものが増えた」「視野が欠けた」といった症状を伴う場合は、網膜剥離の前兆かもしれません。必ず眼科を受診してください。
はじめに
「視界がチカチカする」「突然、光が見える」「視界の端でキラキラしたものが動く」――このような症状を経験したことはありませんか?
こうした現象は一時的で終わることもありますが、場合によっては深刻な目の疾患や脳の異常が隠れている可能性もあります。
本稿では、視界がチカチカする原因として代表的な光視症(こうししょう)、閃輝暗点(せんきあんてん)、眼精疲労の3つに焦点を当て、それぞれの特徴や注意点について解説します。検索ニーズの高いキーワード「視界 チカチカ 原因」「目のチカチカ」に対する信頼性のある情報提供を目的としています。
1. 光視症:網膜の物理的刺激による光の錯覚
光が“走る”ように見える感覚
光視症とは、「実際には存在しない光を感じる」視覚現象です。多くの場合、暗い場所や目を閉じた際に、突然稲妻や閃光のような光が走るように感じられます。これは網膜が物理的に刺激されることで、脳に「光が見えた」という誤った信号が送られるために起こります[1]。
代表的な原因
- ・後部硝子体剥離:加齢に伴い、眼内の硝子体(ゼリー状の組織)が収縮し、網膜からはがれていく過程で網膜が引っ張られ、光視症が生じます。特に50代以降に多くみられます[2]。
- ・網膜裂孔・網膜剥離:網膜が破れたり剥がれたりすることで、強い光視症や視野欠損が出現します。これは失明のリスクを伴う緊急疾患であり、早期治療が不可欠です[3]。
- ・原因:疲労、睡眠不足、カフェイン過剰、ストレス、ドライアイ[4]
早期受診の目安
以下のような症状がある場合は、速やかに眼科を受診してください:
- ・突然のチカチカや光が増えた
- ・黒い影(飛蚊症)が急に増えた
- ・視野の一部が欠けている・黒くなる
これらは網膜剥離の初期兆候である可能性があります。
2. 閃輝暗点:脳の視覚野の血流変化によるもの
“ギザギザ光”から始まる片頭痛の前兆
閃輝暗点とは、視野の中心または周辺部に「ギザギザした光」「チカチカした模様」などが現れ、数分〜30分ほど続いた後に頭痛が始まるという現象です[4]。
片頭痛の前兆(オーラ)として知られており、片頭痛患者の約20〜30%にみられるとされます[5]。
発症メカニズム
閃輝暗点は脳の後頭葉(視覚野)における一過性の血流障害により発生します。一種の“神経の過剰興奮”が視覚異常として現れ、その後の頭痛発作につながると考えられています[6]。
見分け方のポイント
- ・閃輝暗点は両眼の視野に同時に現れることが多く、眼球自体の異常ではありません。
- ・頭痛のない「無頭痛性片頭痛」も存在します。
眼科で眼底異常がなければ、神経内科や脳神経外科での評価が必要です。
3. 眼精疲労:日常的な目の酷使によるチラつき
スマホ・PCによる“視覚疲労”
近年、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイス使用の増加により、長時間の近業作業が目に負担をかけています。
このような状況下で、「視界がチカチカする」「ピントが合わない」「目がまぶしい」といった症状が出ることがあり、これらは眼精疲労の一部とされています[7]。
関係する要因
- ・調節筋(毛様体筋)の過剰使用によるピントの乱れ
- ・ドライアイによる角膜表面の不安定化
- ・睡眠不足・ストレス・自律神経の乱れ
特に20代〜40代の若年層において、「スマホ老眼(調節性けいれん)」との関連が注目されています[8]。
おわりに
「目のチカチカ」は、一時的な疲労サインであることもあれば、失明のリスクを伴う重篤な疾患の前兆であることもあります。
症状が繰り返す、片目だけに強く出る、視野が欠けるといったケースでは、眼科専門医による精密検査が必要不可欠です。
視界の異常を「よくあること」と見過ごさず、適切なタイミングで受診することが、健康な視機能を保つ第一歩となります。
参考文献
[1] 日本眼科学会. 眼科診療クオリティブック. 医学書院, 2020.
[2] Foster PJ, et al. The prevalence of posterior vitreous detachment in an adult population. Ophthalmology. 2004;111(4):647-652.
[3] American Academy of Ophthalmology. Retina and Vitreous. 2022.
[4] Charles A. The pathophysiology of migraine: implications for clinical management. Lancet Neurol. 2018;17(2):174-182.
[5] 日本頭痛学会. 頭痛の診療ガイドライン2021. 医学書院, 2021.
[6] Lauritzen M. Pathophysiology of the migraine aura. Brain. 1994;117(1):199-210.
[7] Sheppard JD Jr, et al. The definition and diagnosis of dry eye disease: report of the TFOS DEWS II Diagnostic Methodology Subcommittee. Ocul Surf. 2017;15(3):276-283.
[8] Rosenfield M. Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic Physiol Opt. 2011;31(5):502-515.