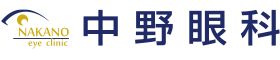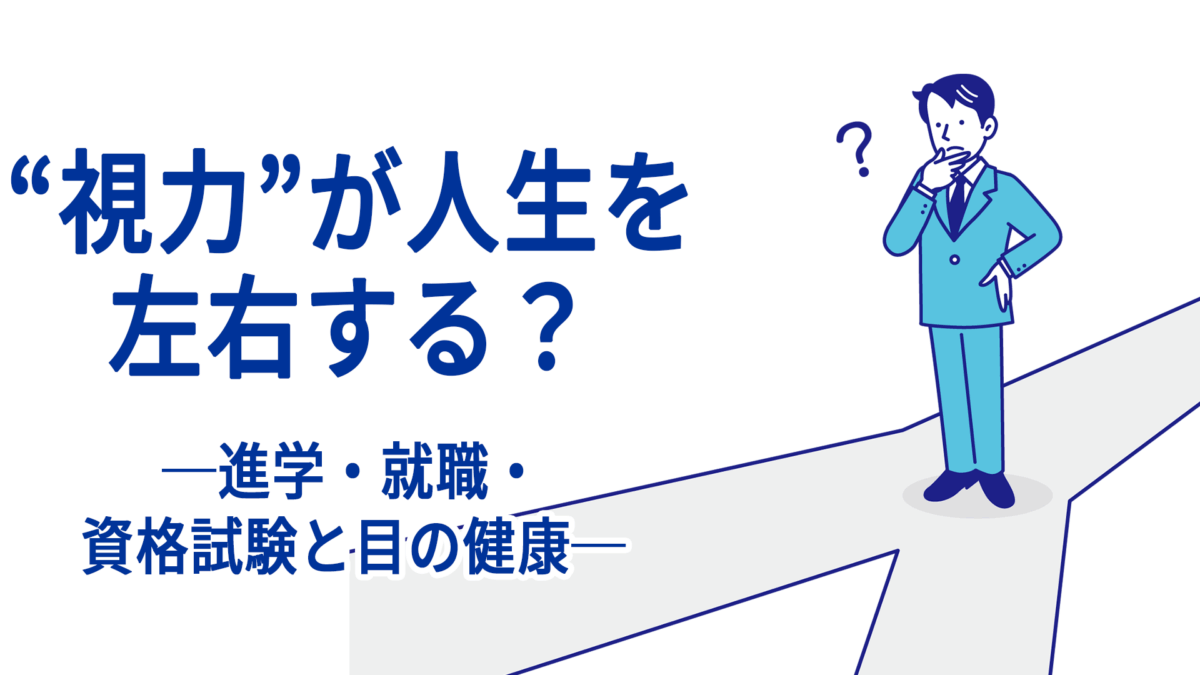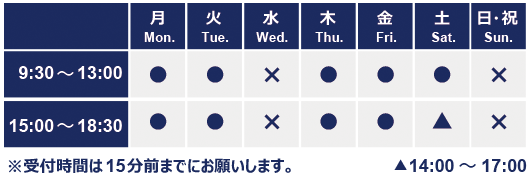よくあるご質問(Q&A)
- Q視力が悪いと、なれない職業はあるの?
- A
あります。航空、鉄道、警察、自衛隊など、多くの分野で裸眼または矯正視力に基づく条件が課されます[1]。
- Q視力が足りなければ、レーシックやICLで補えばいい?
- A
有効な場合もありますが、職種によっては術後の視力安定性・合併症リスクが懸念されることもあります[2]。
- Qメガネやコンタクトでは限界があるの?
- A
視力の矯正自体は可能でも、実務における“見え方”や“視野・動体視力”に制限が出ることがあります。
1. 視力が「キャリア選択の制限要因」になる時代へ
かつて「目が悪くても勉強でカバーできる」と考えられていた時代は、視覚補助技術の発達とともにやや変化してきました。しかし現実には、“視力の条件を満たさなければ応募できない”職種が存在し、人生の選択肢を狭めることになり得ます。特に若年層では「小学生の頃から近視が進み、高校卒業時には裸眼視力が0.1未満」というケースが一般化しつつあります。これは単に日常生活の不便だけでなく、将来の進路・職業選択に直接影響を及ぼす可能性を孕んでいます[3]。
2. 実際に「視力制限」が存在する職業とは?
代表的な職種と視力条件の一例を挙げます(2025年時点の情報に基づく)。
| 職種 | 視力要件(例) | 備考 |
| 航空身体検査(パイロット) | 矯正後1.0以上(両眼)、裸眼視力にも基準あり | 手術歴も報告義務対象[4] |
| 警察官(都道府県による) | 矯正視力0.6以上(両眼) | 採用前健診で判定 |
| 自衛官候補生 | 矯正視力0.8以上 | パイロット職種は裸眼視力重視 |
| 鉄道運転士 | 矯正視力1.0以上 | 動体視力や視野もチェックされることがある |
このほか海上保安官や消防士などでも一定の視力基準があり、中にはレーシックやICLなどの屈折矯正手術が“禁止”または“要報告”対象となっている職種もあります。単に「見える」ようにしたからといって条件を満たすとは限りません。
3. 見落とされがちな“メガネ・コンタクトの限界”
視力矯正手段として最も一般的なのがメガネやコンタクトレンズですが、必ずしもすべての職種・業務において「完全な代替手段」にはなりません。たとえば汗や曇りで視界が遮られる現場職、コンタクト使用が禁止される食品・医療分野、安全眼鏡の併用が困難な工場勤務など、実務で制限が生じる場合があります。さらに強度近視者では矯正後でも“裸眼視力に準拠する制限”が課されることがあり、「よく見えるようにしても受験資格を得られない」という事態も起こりえます。
4. 屈折矯正手術──選択肢を広げる武器か、リスクか
視力制限を突破する手段としてレーシック(角膜屈折矯正手術)やICL(有水晶体眼内レンズ)などの屈折矯正手術が注目されてきました。これらは一定の屈折値内であれば裸眼で1.0以上の視力を得ることが可能であり、資格取得や入職条件を満たす可能性もあります。しかしながら、術後のドライアイやグレア(眩しさ)などの後遺症、長期的な視力変動、職種によっては術歴そのものが懸念材料になることもあり、将来の進路を考慮した“時期・術式選択”が重要です[4]。
5. 進学・就職の“早すぎる諦め”を防ぐために
高校生や大学生の段階で「目が悪いからこの職業は無理」と進路を諦めるケースがあります。しかし、多くの情報は不確かで、最新の基準や矯正技術を知らずに“誤解”で進路を断念している人も少なくありません。オルソケラトロジーやRLRL(赤色光療法)など、近視進行を抑制する手段も登場しており、小児期からの視力管理によって将来の選択肢を確保する取り組みも注目されています[5]。
6. 目の健康は“戦略資産”になる
日々のスマートフォンや長時間パソコン作業、屋内生活の増加により、若年層の近視進行は深刻化しています。目の健康を「今だけの問題」と捉えず、「10年後の自分の選択肢を守るための投資」として捉える視点が、今後ますます重要になるでしょう。「将来、なりたい自分になれるか」は、意外にも“視力”という要素にかかっているかもしれません。
参考文献
[1]警察庁:警察官採用試験視力基準(令和6年度要綱より)
[2]日本航空身体検査基準(国土交通省航空局、2023年)
[3]文部科学省:学校保健統計調査(2022年度)
[4]JAL・ANA採用試験募集要項・身体検査項目(2024年)
[5]Chua WH, et al. “Atropine for the treatment of childhood myopia.” Ophthalmology. 2006