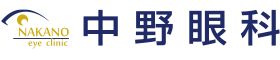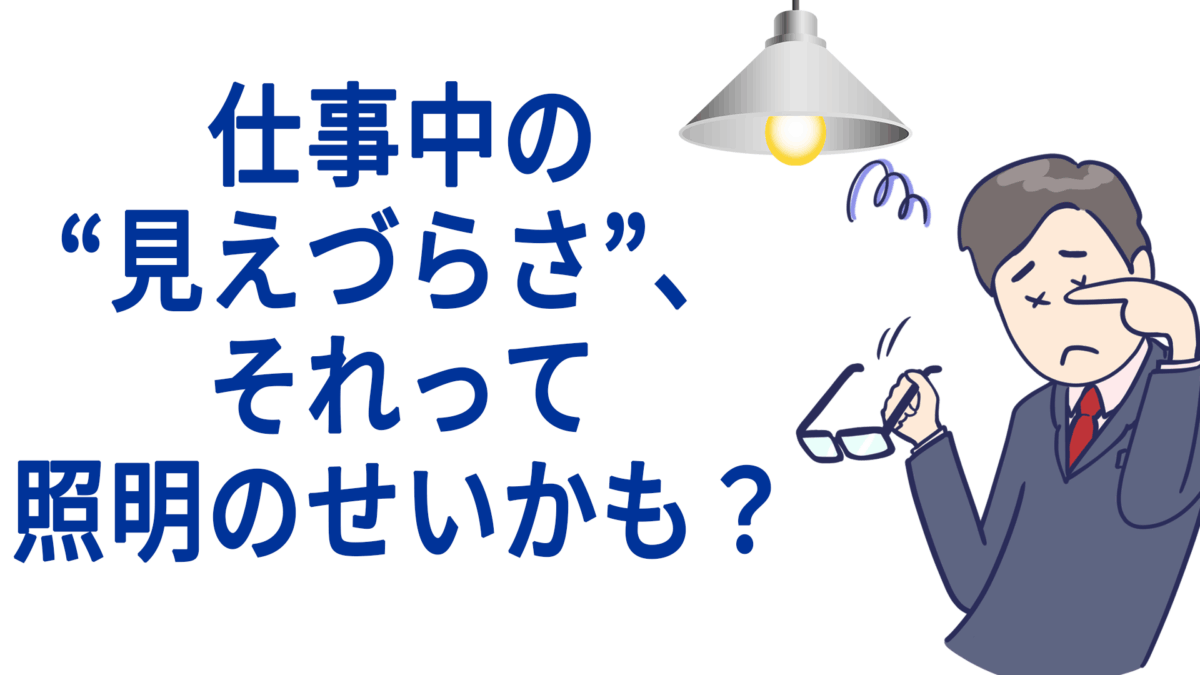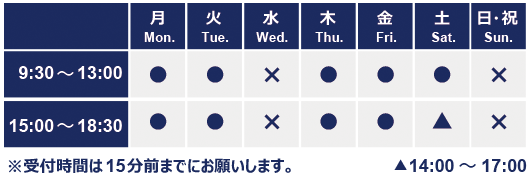よくあるご質問(Q&A)
- Qオフィスや自宅の照明が目の疲れに関係あるの?
- A
あります。照明の種類や配置によって、視機能や集中力に大きな影響が出ることがあります[1]。
- Q白色・青白い光は目に悪いの?
- A
一概に悪いとは言えませんが、青色光を多く含む昼光色は、眼精疲労や睡眠リズムに影響を与える可能性があるとされています[2]。
- Qテレワークで急に目がつらくなったのはなぜ?
- A
照明環境や画面設定、作業姿勢がオフィスと異なることで、視覚的負荷が増している可能性があります[3]。
1. 見えづらさの原因は「照明」かもしれない
「最近、パソコン作業中に文字がぼやける」
「資料にピントが合いにくい」「夕方になると目がかすむ」──
こうした不調に心当たりはありませんか?
視力の問題や眼鏡の度数を疑う前に、照明環境を見直すことが重要です。
オフィス照明の色温度・照度・位置は、目の負担や作業効率に直結します。実際、「目が疲れる 照明」「PC作業 目の不快感」「事務仕事 視力低下」などの検索ワードは、こうした日常的な視覚のストレスを示しています。
2. 照明の種類と“視覚的ストレス”
照明には主に次のような種類があります。
- 昼白色(5000K前後):自然光に近く、事務作業に向くとされるが、青色成分が強いと感じる人も
- 昼光色(6000K以上):白く明るい印象だが、青白い光は眼精疲労や睡眠の質に悪影響を与えることも
- 電球色(2700~3000K):目に優しく、リラックス効果が高いが、細かい作業には不向きな場合も
ブルーライトが多い光は、長時間見つめることで角膜や網膜に微細なストレスを与え、眼精疲労・ドライアイ・睡眠障害を招くことが知られています[2]。特にLED照明では、光のちらつき(フリッカー)が生じることもあり、これが視覚的不快感を助長するという報告もあります[4]。
3. テレワークに潜む「見えない不調」
在宅勤務が増える中、オフィスよりも照明環境が整っていない自宅での作業が当たり前になりました。
- キッチンカウンターやリビングでの作業
- スポット照明や間接照明のみでのPC使用
- モニターの明るさと部屋の照度のミスマッチ
これらが重なると、瞳孔が無意識に開閉を繰り返し、目の筋肉(毛様体筋)が緊張し続ける状態になります。結果として、「見えにくい」「かすむ」「二重に見える」などの症状が出現します[3]。
さらに、テレワークでは画面と紙資料を交互に見る機会が減り、「近距離固定視」になりやすいことも、調節障害の一因とされています。
4. 見直すべきは“照明+習慣”
目の負担を軽減するために、以下のような工夫が効果的です:
- 昼白色または中間色の照明を選ぶ(5000K前後が推奨される)
- 照明の配置は真正面よりもやや斜め上から
- パソコンの画面輝度と部屋の明るさをバランスよく調整
- 20-20-20ルール(20分ごとに20秒、20フィート〔約6メートル〕先を眺める)を習慣化
- ディスプレイに反射が入らないよう、カーテンやスタンドライトを調整
照明というと、つい「明るければ良い」と思われがちですが、“目に優しい明るさ”とは必ずしも最大照度ではありません。人間の目にとっては、「強すぎず・弱すぎず・ちらつかず」が理想です。
参考文献
[1]日本照明工業会:オフィスにおける照明設計のガイドライン,2020年
[2]Oh J. et al. “The influence of blue light on visual performance and eye fatigue”, J Adv Res, 2020
[3]厚生労働省:テレワークと健康に関する報告書(令和4年度)
[4]IEEE PAR1789:LEDフリッカーの人間影響に関する技術ガイドライン,2015年