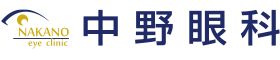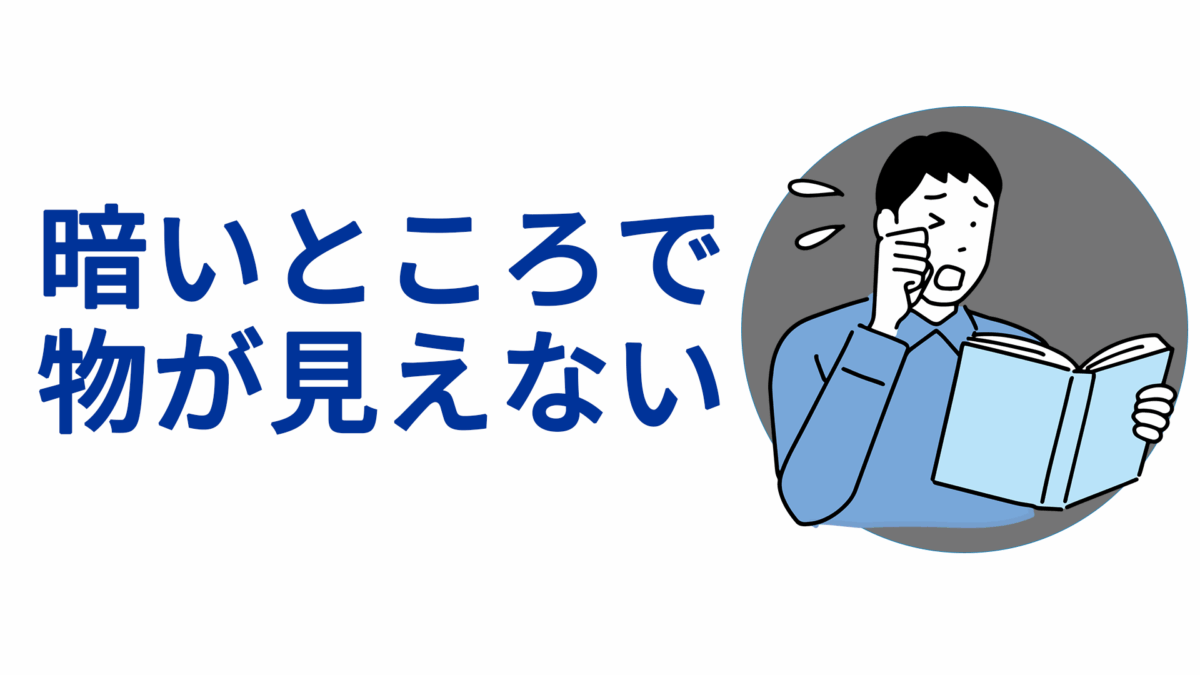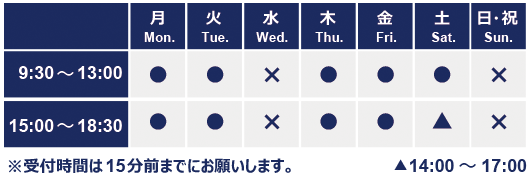夜間や薄暗い場所で物が見えづらくなる症状は、「暗順応障害」あるいは「夜盲(やもう)」と呼ばれます。これは、暗い環境に目がうまく適応できない状態を指し、日常生活に不便をもたらすことがあります。
ただし、このような見えづらさには、重大な目の病気が原因である場合もあれば、年齢や一時的な目の疲れなど、比較的問題のないケースもあります。以下に、原因や症状、対処法について詳しくご紹介します。
主な原因
1. 加齢による視機能の変化
年齢を重ねることで、暗い場所に対する目の順応力は徐々に低下します。これは自然な老化現象であり、ある程度の「暗がりでの見えにくさ」は誰にでも起こり得ます。
2. 眼精疲労や一時的な目の負担
長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用、睡眠不足などによって、目の機能が一時的に低下し、暗い場所で見えにくく感じることがあります。休息をとることで改善するケースが多く見られます。
3. ビタミンA不足
ビタミンAは、視覚に必要な物質(ロドプシン)の合成に欠かせません。偏った食生活や吸収不良などにより欠乏が生じると、夜盲の原因となることがあります。
4. 網膜の異常
網膜色素変性症や加齢黄斑変性症など、網膜の疾患により、光に対する感受性が低下し、暗所での視力に影響を及ぼすことがあります。
5. 白内障
水晶体が濁る白内障が進行すると、光の通過が妨げられ、夜間や暗所で視界がぼやけることがあります。特に「夜間にまぶしく感じる」「暗い場所で見えづらい」といった訴えが増える傾向にあります。
6. 糖尿病網膜症
糖尿病により網膜の血管に障害が生じると、暗順応機能が低下する場合があります。糖尿病をお持ちの方は、定期的な眼底検査が重要です。
7. 遺伝性の疾患
特に若年で進行する暗所視の障害には、遺伝的な要因が関与していることもあります。家族に視覚障害を持つ方がいる場合は、早めの検査が推奨されます。
よく見られる症状
- 暗くなると、物の輪郭がはっきりしなくなる
- 明るい場所から急に暗いところへ移ると、目が慣れるのに時間がかかる
- 薄暗い場所で足元の段差や障害物が分かりにくい
- 夜間の運転で、周囲が極端に見づらく感じる
対処法と予防
1. 栄養状態の見直し
ビタミンAを多く含む食品(にんじん、ほうれん草、レバーなど)を意識して摂取することが推奨されます。ただし、ビタミンAの過剰摂取は逆効果となることもあるため、サプリメント等の使用には医師の指導が必要です。
2.目を休める習慣
目を酷使する生活習慣が原因となっている場合は、定期的な休憩や十分な睡眠を取ることで改善が期待できます。特に、長時間のデジタルデバイス使用後には、目を閉じる・遠くを見るといった習慣が有効です。
3. 適切な照明の工夫
夜間や暗所での見えにくさを軽減するには、住環境に適切な照明を設置することが大切です。階段や廊下などの照度を高めることで、転倒などの事故予防にもつながります。
4.眼科での精密検査
加齢や眼精疲労による一過性の症状と、病的原因による視機能低下とを見分けるためには、眼科での詳細な検査が必要です。眼底検査、視野検査、OCT(網膜断層撮影)などによって原因を特定することができます。
暗所での「見えにくさ」は、軽い目の疲れから重大な病気まで、幅広い原因が考えられます。日常生活に支障が出ていたり、症状が進行しているようであれば、早めの受診をおすすめします。
「見えにくさ」に慣れてしまう前に、専門的なチェックを受けておくことが、目の健康を守る第一歩です。