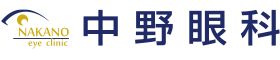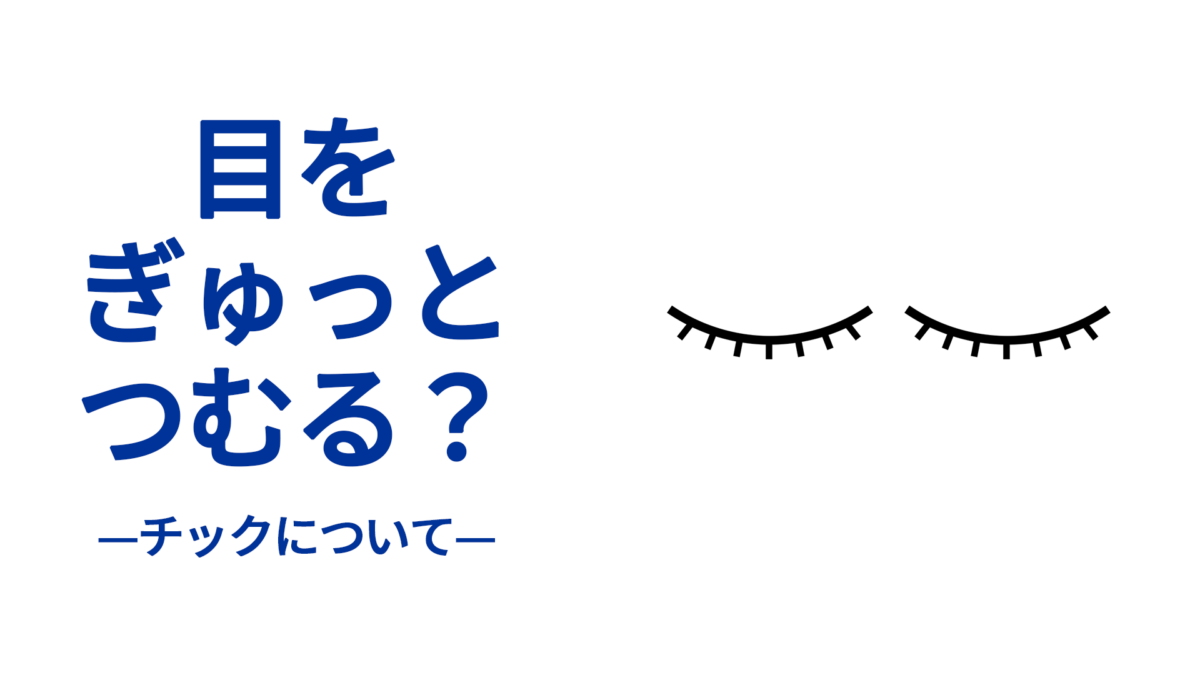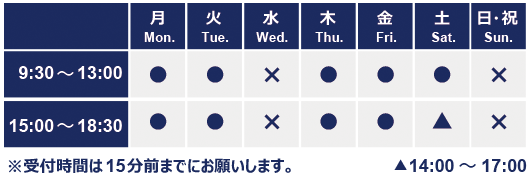1. はじめに
小児において「目をぎゅっとつむる」動作が頻繁に見られることがあります。これは一般に「チック」と呼ばれるもので、一時的なものもあれば、持続するものもあります。本コラムでは、小児のチックの原因、診断、治療、また保護者としてどのように対応すべきかについて解説します。
2. チックとは?
チックとは、自分の意思とは無関係に繰り返される素早い動作や音声のことを指します (American Psychiatric Association, 2013)[1]。主に以下の2種類に分類されます。
- 運動性チック: まばたき、顔をしかめる、肩をすくめるなど
- 音声チック: 咳払い、鼻をすする、短い声を発するなど
目をぎゅっとつむる動作は代表的な運動性チックの一つです。
3. 小児における目をつむるチックの特徴
3.1. 一過性チックと慢性チック
チックは、以下の2種類に分類されます。
| 種類 | 定義 | 例 |
| 一過性チック | 1年以内に消失する | まばたき、目をつむる、鼻をすする |
| 慢性チック | 1年以上持続する | 頭を振る、口を大きく開ける、音声チックを伴うことも |
小児のチックの多くは一過性で、自然に消失することが多いとされています (Leckman et al., 1998)[2]。
3.2. トゥレット症候群との違い
トゥレット症候群は、運動性チックと音声チックが1年以上続くものを指します (Robertson, 2000)[3]。目をつむるチックが他の複数のチックと組み合わさっている場合、トゥレット症候群の可能性を考える必要があります。
4. チックの原因
チックの明確な原因は解明されていませんが、以下の要因が関与すると考えられています。
4.1. 神経学的要因
- ドーパミンの過活動: チックの発生には、脳内のドーパミン系の過活動が関与している可能性が指摘されています (Singer, 2005)[4]。
- 脳の発達: 小児期の神経発達の過程で一時的にチックが出現することがある (Bloch et al., 2006)[5]。
4.2. 環境要因
- ストレスや不安: 学校や家庭の環境が変わると、チックが悪化することがあります (Conelea & Woods, 2008)[6]。
- 注意を引こうとする行動: 無意識に親や周囲の注意を引こうとして発生することがあります。
4.3. 視力との関連
- 視力低下: 目をこする、頻繁にまばたきをするなどの行動がチックと誤認されることがあります。
- ドライアイやアレルギー: 目のかゆみや乾燥が原因で、目をつむる動作が増えることがあります (Kurlan, 2011)[7]。
5. 診断と治療
5.1. 診断方法
チックは通常、臨床診察によって診断されます。以下の点が診断のポイントになります。
- どのような動作が見られるか
- 例えば、「目をぎゅっとつむる」チックが1日に何回あるか、特定の状況で増えるか(例: テレビを見ているとき、宿題をしているときなど)。
- 頻度と持続期間
- 1日何回繰り返されるか、発症してどのくらいの期間経っているか。
- 1年以上続いている場合は慢性チック、1年未満なら一過性チックの可能性が高い。
- 他の神経症状の有無
- 頭を振る、肩をすくめる、声を発するなどの他のチック症状があるか。
- 強迫行動(手を何度も洗う、物の配置にこだわるなど)があるか。
- 家庭や学校での影響
- チックによって学校生活に支障が出ていないか(例: 授業中に頻繁に目をつむるため、黒板が見えにくくなっている)。
- 家庭内での様子(例: 注意を受けるとチックが増える、リラックスしているときに減る)。
眼科的な問題(視力低下やドライアイなど)を除外するため、眼科検診も重要です。視力検査や涙液分泌量の測定を行い、目の異常がないかを確認することで、チックと目の健康状態を区別することができます。
眼科的な問題(視力低下やドライアイなど)を除外するため、眼科検診も重要です。
5.2. 治療と対応
ほとんどのチックは治療を必要としませんが、以下の方法で軽減できる場合があります。
| 治療法 | 方法 | 効果 |
| 環境調整 | ストレスを減らす、リラックスできる時間を作る | チックの頻度を軽減 |
| 認知行動療法 | 習慣逆転療法(HRT)を用いる | 効果的にチックを抑える (Piacentini et al., 2010)[8] |
| 薬物療法 | ドーパミン拮抗薬(リスペリドンなど)を使用 | 重症例に限られる (Scahill et al., 2006)[9] |
6. まとめ
小児の目をぎゅっとつむるチックは、多くの場合一時的なものであり、自然に消失することが多いです。神経学的要因やストレス、視力の問題が関与することもあるため、適切な診断が重要です。保護者としては、無理にチックをやめさせようとせず、環境調整を行うことが望ましいです。
参考文献
- American Psychiatric Association. (2013). “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).”
- Leckman, J. F., et al. (1998). “Course of tic severity in Tourette syndrome: The first two decades.” Pediatrics.
- Robertson, M. M. (2000). “Tourette syndrome, associated conditions and the complexities of treatment.” Brain.
- Singer, H. S. (2005). “Tourette’s syndrome: from behaviour to biology.” The Lancet Neurology.
- Bloch, M. H., et al. (2006). “Neuroanatomy of childhood-onset obsessive-compulsive disorder.” Biological Psychiatry.
- Conelea, C. A., & Woods, D. W. (2008). “The influence of contextual factors on tic expression in Tourette’s syndrome.” Journal of Child Psychology and Psychiatry.
- Kurlan, R. (2011). “Clinical practice: Tourette’s syndrome.” New England Journal of Medicine.
- Piacentini, J., et al. (2010). “Behavior therapy for children with Tourette disorder.” JAMA.
- Scahill, L., et al. (2006). “Contemporary assessment and pharmacotherapy of Tourette syndrome.” NeuroRx.